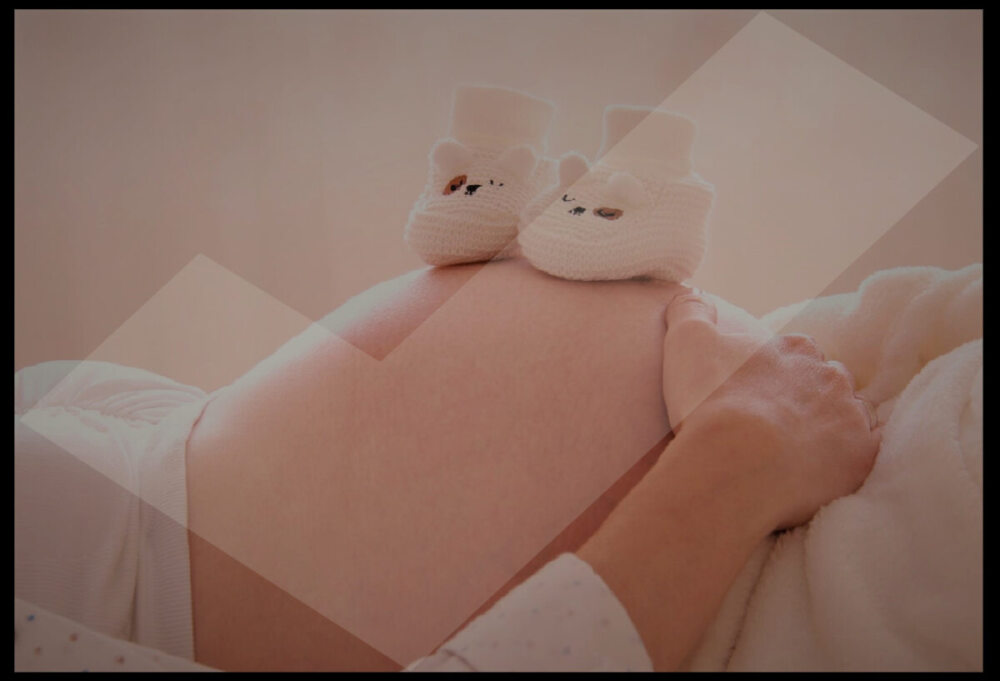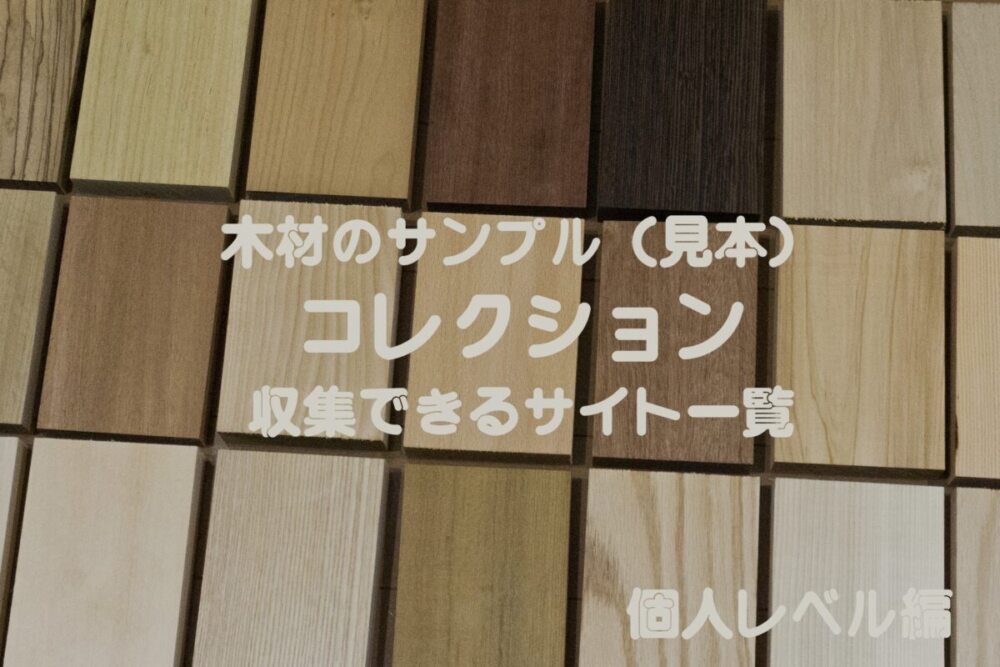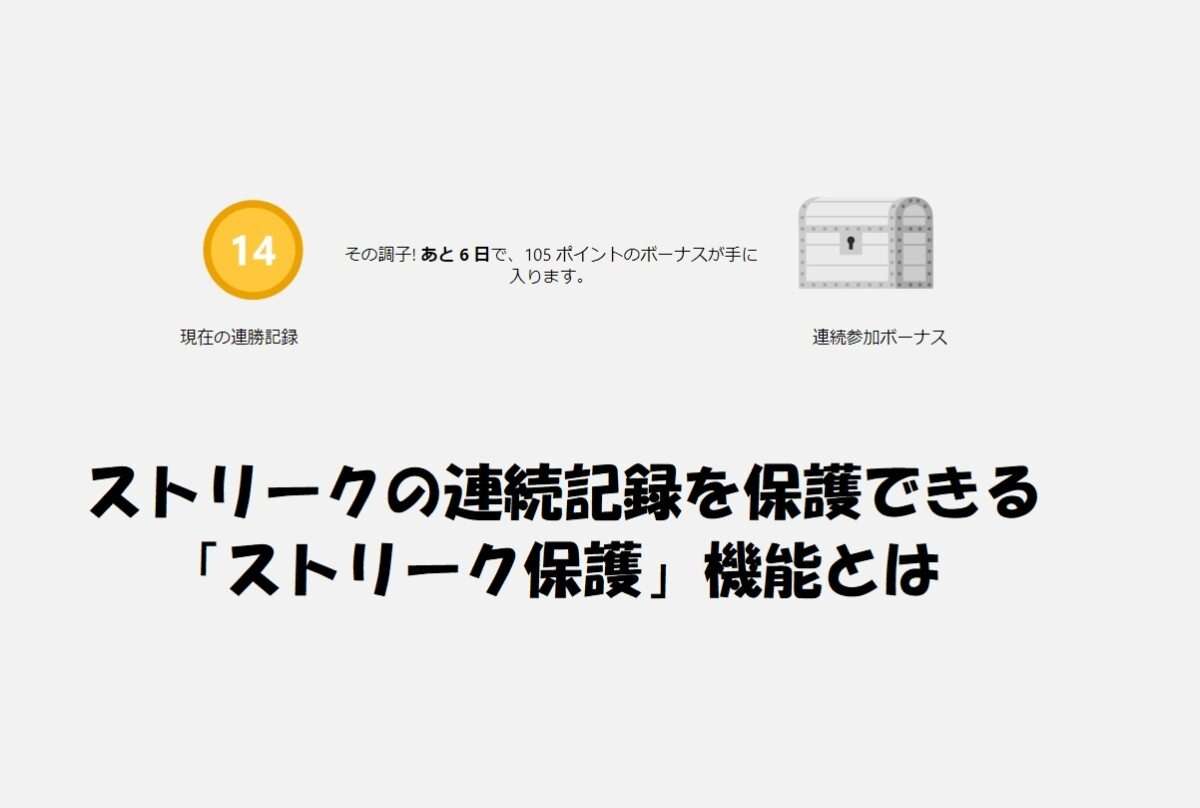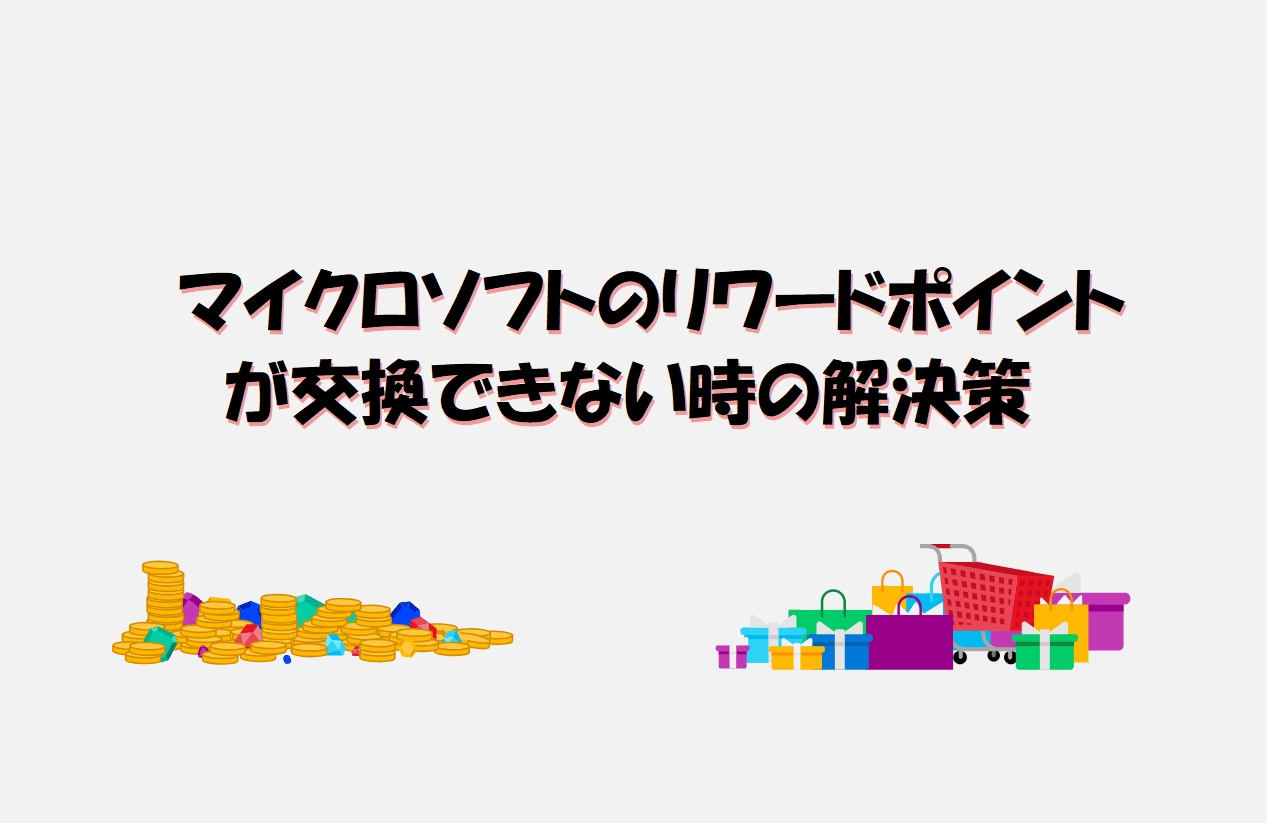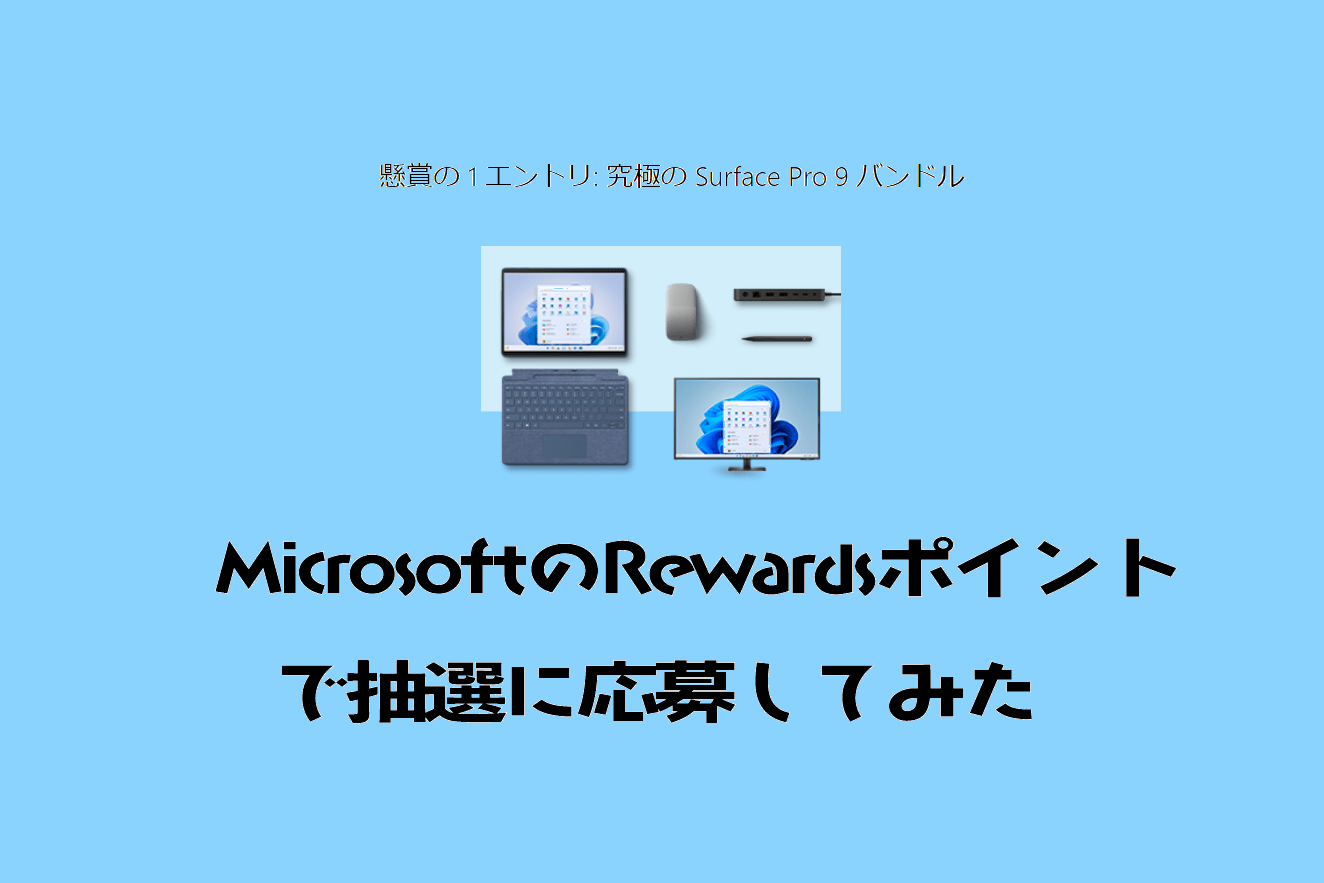認定こども園の良いところは3歳以上であれば、働いていなくても子供を預けることができるところです。
通常、保育園だと仕事を辞めてしまうと退園になり、子供が転園して新しい環境でストレスを抱える心配があります。
しかし、認定こども園であれば支給認定を切り替えるだけで子供が通いなれた園に在園することができるので母子共にメリットが大きいです。
なにかの諸事情で仕事を辞めなくてはいけなくなった場合でも、焦らずに仕事を探すことができます。

目次
認定こども園の入園資格

幼稚園と保育園の機能を持ち合わせた新しい施設が「認定こども園」です。
0歳から5歳までの子供を預かってもらえます。
0歳~2歳までは入園資格や保育時間などは保育園と一緒
3歳~5歳までは入園資格は保育を必要とする子供+1号認定(※)の子供が入園できます。
※1号認定とは保育の必要がない子供(通常なら幼稚園に入る子供)
認定こども園について
認定こども園は幼稚園と保育園のいいとこどりの施設です。
幼稚園は登下校時間はみんな一緒ですが、認定こども園は働いている親の子供もいるため保育時間はみんなバラバラです。
それにともない保育料も世帯収入によって決められているので、幼稚園のように一律ではありません。
保育内容も認定こども園は保育よりも独自の取り組みとして『教育』に力を入れている園が多いです。
3歳以下の子供もいるので、幅広い年齢の子たちと一緒に触れ合えます。
そして親が仕事を辞めても子供たちは認定こども園に通うことができるので、保育所のように仕事をしているかどうかは問われません。
親の都合で子供の保育環境がが変わらないと言ったメリットがあります。
幼稚園はPTA活動とか親が参加しなければならないものが多いですが、認定こども園は働いる親もいるためママ友との交流もすくないです。
認定こども園を選ぶ時の注意点
- 雑費が高い
- 長期休暇がない。(夏休み・冬休み)

雑費が高い
今は、3歳以上の子供は保育料は無償化されていますが、問題は保育料以外にかかる雑費です。
この雑費、認定こども園は結構高くて、私が通っている認定こども園は月々1万円前後かかっていました。
認定こども園は教育にも力を入れているので、雑費は幼稚園と同じか、それよりも高い傾向にあります。
長期休暇がない。(夏休み・冬休み)
長期休暇がない。(夏休み・冬休み)
働いてる親の子供を保育する機能をもっているので、長期休暇がありません。
兄弟がいて、上が小学生だった場合、夏休みや冬休みなどの長期休業などでも下の子は認定こども園に通う事になります。
休ませても良いですが、長期に休むのはちょっと気が引けたりします。

支給認定を1号認定に切り替えるのは事務手続きだけでOK
私の場合、諸事情で仕事を続けるのは無理かな?って思った時に幼稚園という選択もありました。
しかし、通っていた保育園が途中から認定こども園になったため、新たに幼稚園を探す手間が省けました。
実際、幼稚園も検討していて希望の幼稚園に電話もしみましたが、定員オーバーで受け入れてもらえないこともあります。
やりたい盛りの4歳児を家で退屈させずに、1号認定に切り替えるだけで在園できるのは助かりました。
手続きは認定こども園に書類を提出するだけで済みました。
認定こども園に在籍させるかはお金次第⁉

一つ言うなら毎月かかる雑費が高いです。
保育園と幼稚園の機能を併せ持つ認定こども園は、幼稚園のような教育をしているため、教材費や指導料など色々な形で月々の費用が高くなりがちです。
仕事を辞めて、毎月の支払いがきつく感じたら、違う園に転園することや、また仕事を再開するなど考える必要はあると思います。